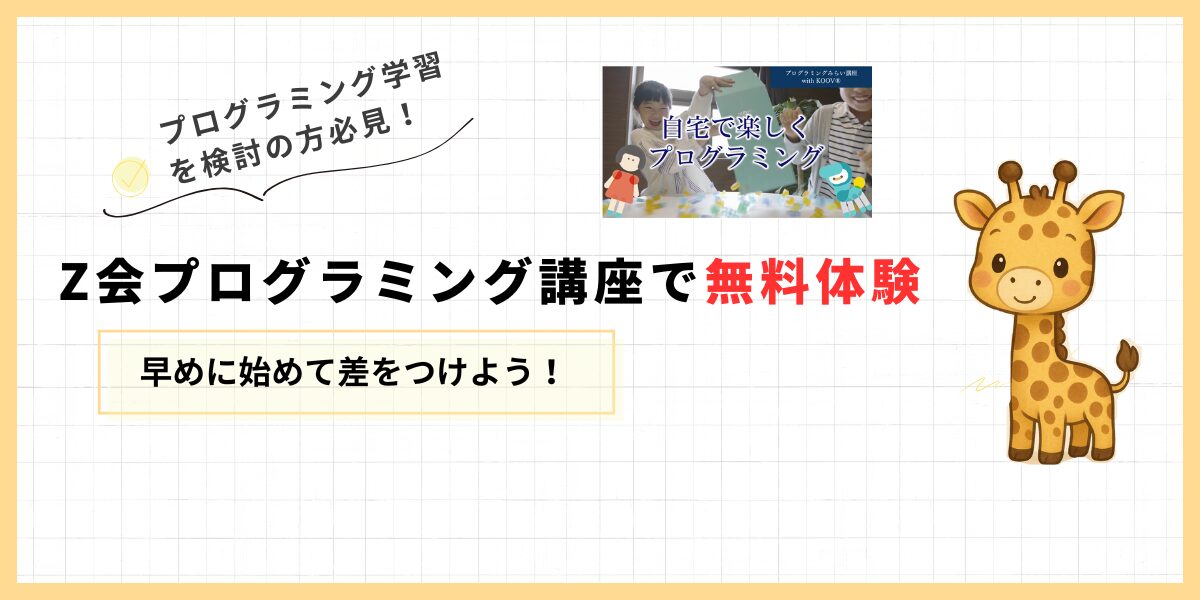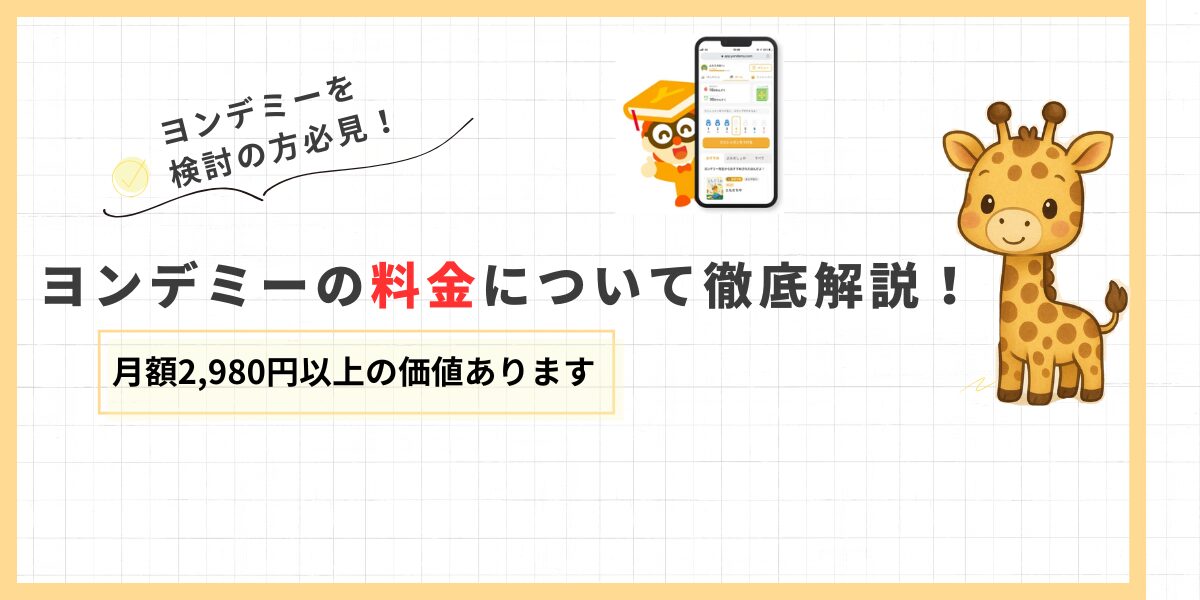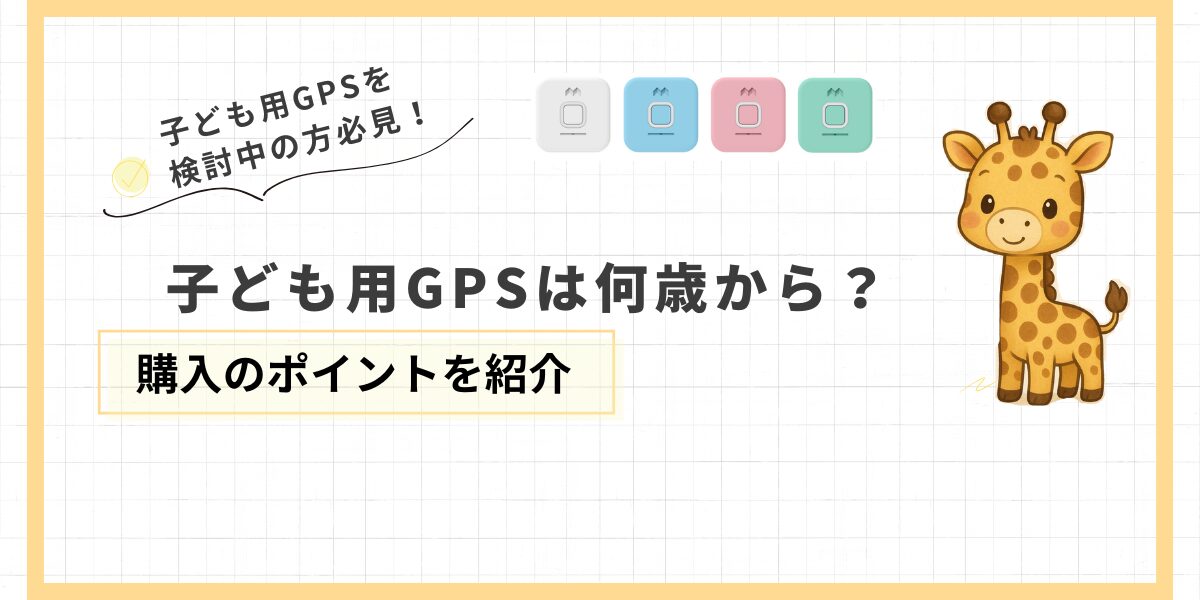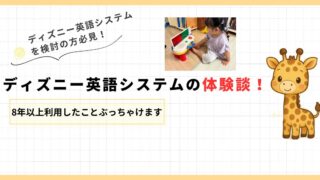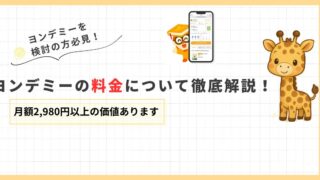・正しい「褒め方」と「認め方」
・認めることで自己肯定感も上がる
・プロスポーツの現場から子育てを考えてみる
・親の使う言葉は子どもに与える影響が大きい
子供を「褒める」「認める」というのは大切!
このことは、多くの人がわかっていることでしょう。
褒めたり認めたりすることで、その子どもの自己肯定感も上がるかもしれません。
しかし、やり方や考え方を間違えると子どもには悪影響を与える可能性もあります。
正しい褒め方や認め方を実例を交えて紹介していきます!
子どもを「褒める」と「認める」の違いとは

子どもだけでなく人間は他者に褒められたらうれしいものです。
子どもは自分が大好きなお母さん、お父さんが褒めてくれるのはこの上ない喜びでであり、自己肯定感も上がります!
私自身も親が喜んでくれているのは非常に嬉しかった記憶があるし、今もそのことは変わりません。
しかしその「褒める」は「認める」とも使い分けることができます!
そのことをしっかり意識するためにも意味を確認しましょう。
「褒める」とは
褒めるとはどういう意味なのでしょうか。
人のしたこと・行いをすぐれていると評価して、そのことを言う。
たたえる。 祝う。ことほぐ(言葉で祝福すること)。
子どもが上手に絵を描いたり、テストで100点取ったりしたことに対して「すごいね」と伝えることなどは「褒める」といえる行為です。
「認める」とは
対して認めるとはどのような意味があるのでしょうか。
目にとめる。存在を知覚する。気づく。
見て、また考えて確かにそうだと判断する。
正しいとして、また、かまわないとして受け入れる。
能力があると判断する。
気をつけて見る。じっと見る。
言葉の意味としては「褒める」のほうが相手に対して良いことをしているイメージがあるような気がします。
「認める」の意味はしっかり見て考えて認識したうえでの行為ということが分かります。
子どもを「褒める」は注意点もある?「褒める」より「認める」ことが重要

「褒める」は使い方を間違えると子どもに悪影響を与えかねません。
「褒める」ことの効果と注意点を考えていくとともに、
子どもを「認める」ことの重要性について考えていきます。
「褒める」ことによる効果と注意点
褒めることの効果
- 挑戦する気持ちや前向きに取り組む気持ちが芽生える
- 自己肯定感を上げることができる
- 他人にも優しくできる心が育つ
- 親子間でも信頼関係が育つ
褒める時の注意点
- 何でも褒めることはNG
- 結果だけを褒めない
- 他人と比べて褒めない
- 何でも褒めすぎると慣れてしまう
褒めることは良いことですが、何でもかんでも褒めすぎると逆効果になってしまう可能性があります。
何事もそうですがやりすぎてしまうとその効果や価値を下げてしまいますね。
「認める」ことの例
認めることの例
- こぼしたところを拭いてくれたね
- 毎朝縄跳びの練習をしてるね
- 消しゴムのカスもゴミ箱に入れてるんだね
- お茶碗の中だけでなく外側も洗ってるね
- 使った物をもとの場所に戻してくれたね
普段からしっかり見ていないとできないことですね!
認めるとは相手の行動を具体的に言葉で伝えて褒めていることが分かります。
では具体例と照らし合わせて「褒める」と「認める」の違いを考えてみます。
「褒める」と「認める」の違いを考えてみる
子どもがマラソン大会で10位という結果を出したとします。
「褒める」場合
「褒める」のアプローチ
- 10位はすごいね!
- やったじゃん
- よく頑張ったね
もちろんこれも良い言葉掛けです。
しかし、このようなケースであればどうでしょう?
本当はもっと走れたけど手を抜いていた。。。
途中で歩いてしまった。。。
このようなことを子どもが思っている状況で「褒める」だけでは、
- あれぐらいでいいのか
- 手を抜いて走ったのに褒めてくれるんだ
- 本当に自分のこと見てたのかな
と思うかもしれません。
「認める」の場合
「認める」のアプローチ
- 走り切ったことを労う
- 走ってどうだったのか聞いてみる
- 最後までやり切ったことを褒める
大事なことは相手の話も聞いたうえで言葉をかけることです。
その中で途中に手を抜いてしまったということを聞いたとしても
「10位という結果もすごいし、何よりも最後まで走り切ったことがお父さんは嬉しいよ。
長距離は誰がやってもしんどいものだし、途中で苦しかったろうけど最後までやり切ったことがほんとにすごい。
次は最後まで全力で行けるように応援してるよ。」
というようなアプローチを受けるとどうでしょうか?
10位という結果だけでなく、やり切ったその子ども本人をすごいと認めて、それによって嬉しい気持ちになったと伝える。
そのことにより
何よりも自分が走り切ったことを認めて喜んでくれている。
最後までやり切った自分はすごいんだ、次はもっと頑張ってみよう
という思いになり大切な人を喜ばすことができた!
という自己肯定感を得るかもしれません。
その子どもが行った行為に対して結果だけでなく、そこに至るまでの過程に対して具体的な言葉で伝える。
それにより自分自身が幸せな気持ちになったと伝える。
そのように「認める」ためには、その子どものことを普段からしっかりと見てあげることが必要ですし、親自身も子どもの気持ちに寄り添って言葉を選ばなければなりません。
「褒める」という行為がマイナスであることは決してありません。
「認める」ということを理解して「褒める」言葉をかけることで子どもに対して非常にいい影響を与えることができるでしょう。
子育てにおける大切なことをプロスポーツの指導から考えてみる

プロスポーツの現場では様々な指導が行われていますが、認めるという指導を行っているプロスポーツの監督が広島カープの新井貴浩監督です。
ここから子育て繋げれるものがあると思うのでご紹介させていただきます。
新井貴浩とは?経歴や成績
広島県広島市出身の元プロ野球選手
広島カープや阪神タイガースで選手として活躍
ホームラン王やMVPを獲得
非常に明るくてムードメーカー
華やかな経歴ですが、若手の時は先輩や指導者には厳しく鍛えられたという過去があるみたいです。
プロスポーツの現場でも行われている指導方法や考え方
過去に自分自身は非常に厳しく指導を受けた新井貴浩監督ですが、監督となりどのような指導を行っているのでしょうか。
- 徹底的に選手を信じる
- 話を直接聞きに行く
- 一緒に汗を掻く
- 否定的な言葉は使わず前向きな言葉をかけ続ける
プロスポーツという厳しい世界の中でこれをやり続けているのは本当にすごいことです!
他の分野でも指導や考え方は子育てにも活かせる
新井貴浩監督は日頃から気を付けていることがあるといいます。
「監督はチームの顔、よくも悪くも監督の顔がチームの顔になってしまい、選手にも影響があるので気をつけている」
監督がいかに影響力があるのかということを肝に銘じて行動していることが分かります。
家庭に置き換えると
親の態度や言動は子どもに大きな影響を与える
ということを忘れずに行動していると置き換えられます。
新井貴浩監督が実際に行った指導を子育てに置き換えて考えてみます。
監督就任時にチームみんなを家族と称して、みんなのことを好きだと伝えた
↓
子供に対して愛していると伝える。
選手一人一人に思いを伝えて、決して見捨てないから一緒に戦おうと伝えた
↓
子供のことを信じて応援し続ける
選手の長所を褒めてそこをもっと伸ばすように伝える
↓
子供の思いを知ることに努めて、そのことを認めて伸ばす声掛けをする
プロスポーツという大人の世界でも同じことなんですね。
自分自身という存在を認めてもらえた。
と感じればもっと頑張ろうと思ってくれるでしょう!
まとめ
今回の記事をまとめますと、
「褒める」だけでなくその子どもの存在自体を「認める」ことが大切
ということを書きました。
そして、家庭のリーダーである親が明るく前向きな言葉や気持ちでいることは子どもに良い影響を与えます。
これらのことをやり続けることは簡単ではないかもしれません。
しかし親として成長するためにも頑張らなければならないと感じます。
子育てを頑張る皆さまが幸せな毎日を過ごせるように応援するとともに私も頑張って行きます!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

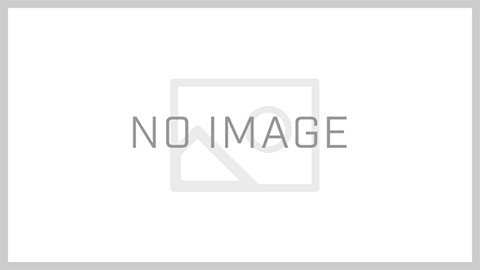
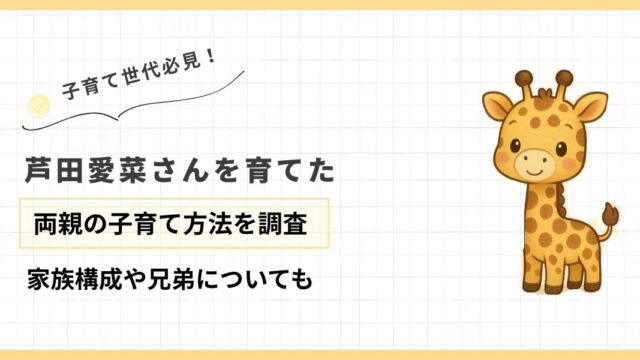




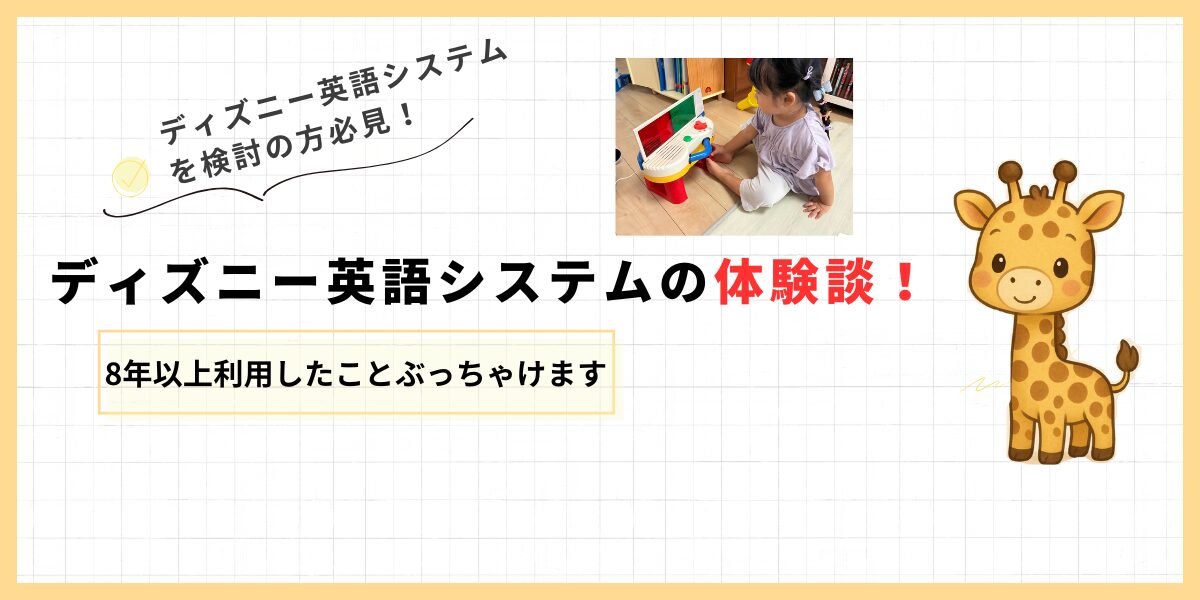 ディズニー英語システムはオススメ!無料サンプルや無料体験もあるから始めやすい!
ディズニー英語システムはオススメ!無料サンプルや無料体験もあるから始めやすい!